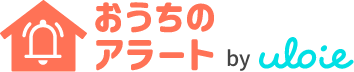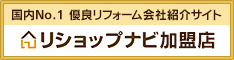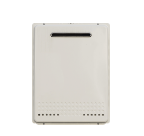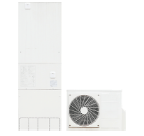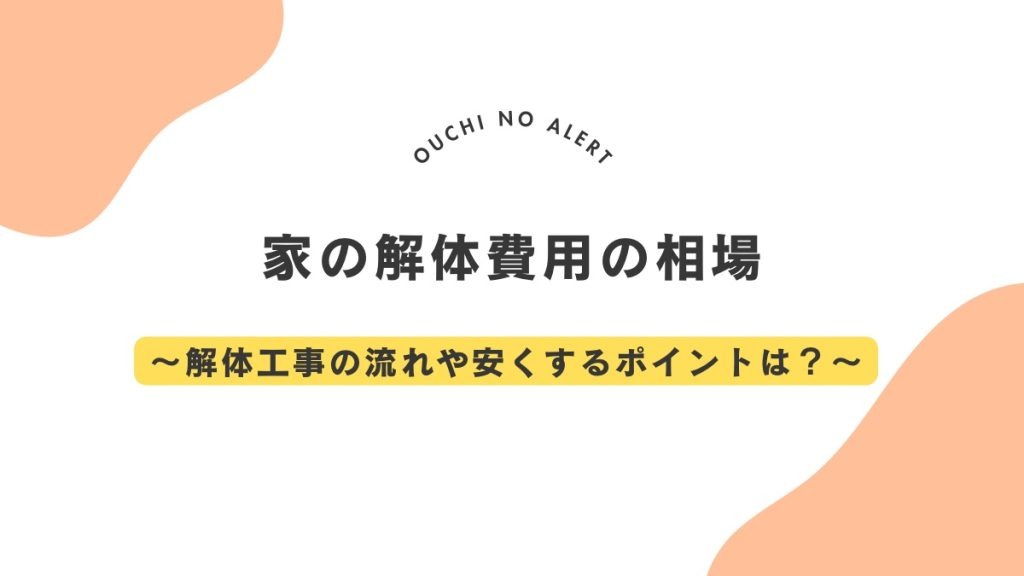
家の売却を考え始めたものの、なかなか買い手がつかない…。そんなときに「建物を解体した方が良いのだろうか?」と考えたことはありませんか?
そこでこの記事では、一軒家の解体の費用相場と実際の解体工事の流れなどをご紹介します。建物の解体を検討している方はぜひ参考にしてみてくださいね。
1. 解体費用の相場とその決定要因

家の解体費用は、全国的に平均して50万円〜300万円程度とされています。
この幅は、建物の構造や広さ、立地条件、そして使用されている建材の違いなど、さまざまな要因によって大きく変わってきます。以下で詳しく解体費用を決定づける要因を見ていきましょう。
1-1. 建物の構造
建物が木造か鉄骨造か、またはRC造(鉄筋コンクリート造)かによって、解体作業の難易度が異なります。基本的には、硬い構造体の建物ほど解体に手間がかかるので、解体費用がかさむと考えて良いでしょう。
例えば、木造の建物は比較的解体が簡単で費用も抑えられますが、鉄骨造やRC造の建物の場合は重機の使用が必須となり、その分費用が高くなります。
1-2. 建物の広さ
解体費用は、建物の広さにも大きく影響されます。一般的に、解体費用は坪単価で計算されるため、広い建物ほど総費用も高くなります。
例えば、二階建ての場合は当然、平屋よりも壊す面積が広くなるので費用が嵩みます。
また、地下階がある場合には埋め立て作業などが追加で発生する可能性があるため、費用が高くなることもあります。
1-3. 立地条件
建物が建っている場所の条件も重要な要素です。傾斜地や極小地などの重機が入りにくい場所や、周囲に住宅が密集していて防音や防塵の配慮が必要な場合、追加の作業が必要となり、その分費用も増えることがあります。
1-4. 使用されている建材
解体する建物にアスベストなどの有害物質が含まれている場合、特別な処理が必要となり、費用が大きく上がることがあります。
アスベストとは、「せきめん」や「いしわた」とも呼ばれる天然の鉱物繊維のことで、熱や摩擦に強い特徴を持つことから一時期自動車や電化製品の材料としても使用されていました。現在では発がん性などの有害性が問題視され、使用を禁じられていますが、1975年以前に建てられた建物にはこの材料が使われている可能性があります。
この有害物質の除去には専門的な技術が求められるため、結果として費用にも関わってくる点を押さえておきましょう。
2. 解体費用の内訳

前章で解体費用を決定づける要因を大まかにご紹介しました。
本章ではさらに詳しく、家屋を解体する際の費用の内訳をご紹介していきます。ご自分の住宅と照らし合わせながら、当てはまる項目を概算してみてください。
2-1. 建物の取り壊し費用
建物の取り壊し費用は、実際に建物を解体するための基本的な費用です。この費用は主に以下の要素によって決まります。
①建物の構造
木造住宅の場合、解体が比較的容易なため、1坪あたり3万円〜5万円が相場とされています。
鉄骨造住宅になると、構造が頑丈な分、解体にも手間がかかり、1坪あたり4万円〜6万円程度になります。
鉄筋コンクリート(RC)造住宅は最も頑丈で解体に時間と労力が必要なため、1坪あたり6万円〜9万円が一般的です。
②建物の大きさ(延床面積)
建物が大きいほど、解体に必要な時間や労力も増えるため、総費用も高くなります。例えば、30坪の木造住宅を解体する場合、30万円〜150万円程度が目安となります。
③立地条件
建物が密集した住宅地にある場合や、道路が狭く重機が入りにくい場所では、手作業が増えるため費用が上乗せされることがあります。逆に、広い道路に面した場所や周囲に十分なスペースがある場合は、効率的に解体作業を進められるため、費用を抑えられる可能性があります。
2-2. 廃棄物の処理費用
廃棄物の処理費用は、解体作業によって生じた不要な素材やゴミを適切に処分するためにかかる費用です。処理する廃棄物の種類や量によって費用が変動するため、見積もりからさらに変動する可能性もあります。なるべく多めに見積もっておく方が安心かもしれません。それでは以下で費用の参考をご紹介していきましょう。
①一般的な廃材
木材やコンクリート、金属類などは、種類ごとに分別して処理されます。こうした一般的な廃材の処理費用は、1立方メートルあたり1万円〜2万円が一般的です。
②有害物質を含む廃材
アスベストやPCBなどの有害物質を含む建材が使用されている場合、専門的な処理が必要となり、費用も高額になります。例えば、アスベストの除去には1平方メートルあたり1.5万円〜8万円がかかることがあります。
③廃棄物の量
解体する建物が古く、内部に多くの不用品が残っている場合、その分廃棄物の量が増え、処理費用も高くなります。事前に不用品を整理・処分しておくことで、廃棄物処理費用を抑えることができます。
2-3. 付随する工事費用
解体作業には、建物の取り壊しや廃棄物処理以外にも、さまざまな付随する工事費用が発生することがあります。
①各種申請・手続き費用
解体工事を行なう際には、自治体への「建設リサイクル法」に基づく届出や、近隣住民への事前挨拶などが必要です。これらの手続きにかかる費用や時間も考慮する必要があります。
②ライフラインの撤去費用
電気、ガス、水道などのインフラ設備を安全に撤去・停止するための費用が発生することも忘れてはいけません。各サービスごとに1万円〜3万円程度かかると見積もっておきましょう。
③地中埋設物の撤去費用
あまり一般的ではないかもしれませんが、解体作業中に古い浄化槽や地中梁、埋設物などが発見された場合、それらを撤去するための追加費用が必要となることがあります。状況によりますが、10万円〜50万円程度の費用がかかるケースもあります。念の為こうした可能性も念頭に入れておくとスムーズです。
④整地費用
さらに、解体後の土地を平らで綺麗な状態に整えるための費用です。土地の状態や広さによって異なりますが、一般的には5万円〜20万円程度となります。
⑤仮設工事費用
解体作業中の安全対策として、仮囲いや足場を設置するための費用が必要です。工事全体の規模や期間に応じて変動しますが、大体10万円〜30万円程度が目安です。
3. 家の解体工事の流れ

解体工事の全体的な流れを把握しておくことは、スムーズな準備や費用管理のために大切です。以下に、解体工事の一般的なステップについて詳しく見ていきましょう。
3-1. 現地調査
解体工事の見積もり依頼を行なったあと、まずは解体業者が現地を訪問し、建物や周辺環境の状況を詳細に確認します。この調査では、建物の構造や立地条件、周囲の環境など、解体に際して考慮すべきポイントを洗い出します。
①立地条件の確認
建物が密集した住宅地にある場合、騒音や振動対策が重要となります。また、重機の搬入が難しい場合は、その対策も必要です。こうした条件に応じて、工事の進め方や費用が変わってきます。
②周囲への影響の確認
近隣住宅への配慮や、工事中の安全確保についても、この段階で計画されます。とくに古い住宅地では埋設物が見つかることも。埋設物の処理方法についても併せて検討されます。
3-2. 家屋調査
次に、建物の構造や使用されている建材についての詳細な調査を行います。この調査では、とくに有害物質(例えばアスベスト)の有無を確認することが重要です。
①建材の調査
壁材や床材に有害物質が含まれているかを確認し、それに応じた適切な処理方法を計画していきます。アスベストが含まれている場合は安全に配慮し、専用の防護装備を使用したうえでの撤去が必要なため、追加費用がかかることがあります。
②解体方法の選定
建物の構造によっては、解体に適した方法を選ぶ必要があります。鉄骨造やRC造の建物では、重機を使用する大掛かりな作業が必要です。
3-3. 解体工事の実施
準備が整ったら、いよいよ解体作業の開始です。
①重機の使用
建物の大部分は重機で解体されます。大きな建物の場合、作業は数日から数週間にわたることも。また、手作業が必要な部分(例えば、狭いスペースや細かな仕上げ部分)もあるため、状況に応じて作業方法が調整されます。
②騒音や振動の対策
解体作業中は騒音や振動が発生します。近隣住民への影響を最小限に抑えるために、防音シートや振動を抑える機材を使用します。
3-4. 廃材処理と整地
解体作業が完了すると、次に廃材の処理と整地作業を行ないます。この段階で、土地が平らで清潔な状態に整えられます。
①廃材の処理
解体によって生じた廃材は、種類ごとに分別され、適切に処分されます。有害物質を含む廃材なども専門業者によって処理されます。
②土地の整地
解体後の土地は、更地として新たに利用できる状態に整えられます。地面を平らにならす作業に加え、必要に応じて地面を固める作業も行なわれます。
4. 解体費用を安く抑えるためのポイント

解体工事は何かと予想外の出来事も多く、当初の見積もりからさらに出費が増えることも。そこで解体費用を抑えるために、いくつか工夫できるポイントを押さえておきましょう。
4-1. 自分でできる準備作業
まず、解体業者に依頼する前に、自分でできる準備作業をしておくと、全体の費用を抑えることができます。
①不用品の処分
家の中にある不用品や、使わなくなった家具などは、事前に自分で処分しておくと、業者にお願いする分が減るため、その分費用が節約できます。粗大ゴミとして自治体に依頼したり、リサイクル業者に買い取ってもらうのもひとつの手です。
②庭木の剪定や整理
庭に生えている木や植物を自分で剪定したり整理しておくと、業者の作業がスムーズになり、時間と費用の削減につながります。とくに、根が深く張っている植物や大きな木は、事前に除去しておくと良いでしょう。
4-2. 助成金の活用
助成金の活用も大きなポイントです。解体費用を補助する助成金制度を提供している自治体が増えており、これをうまく活用することで、解体費用の一部をカバーすることができます。
①助成金の内容を確認する
お住まいの地域でどのような助成金が利用できるか、事前に市役所や区役所で確認することをおすすめします。例えば、古い家屋を解体する場合や、アスベストを含む建材の処理が必要な場合、特別な助成が受けられることがあります。
②助成金申請の手続き
助成金を利用するには、申請手続きが必要です。申請には期限があることも多いので、解体を検討し始めたら早めに調べておくと安心です。
4-3. 解体業者の選び方
解体費用を抑えるためには、業者選びも重要なファクター。信頼できる業者を選ぶことが、無駄な費用を避けるための基本となります。
①複数の業者から見積もりを取る
まず、複数の業者に見積もりを依頼し、費用の比較を行なうことが大切です。この際、費用だけでなく、サービス内容や過去の実績、口コミなども確認して、総合的に判断すると失敗が少ないでしょう。
②業者の信頼性を確認する
解体業者の中には、安価に見せかけて後から追加費用を請求するケースもあるため、事前に契約内容や追加費用の有無をしっかり確認しておきましょう。また、過去に同じ業者を利用した知り合いがいる場合、その人の意見を参考にするのも良い方法です。わからないところをしっかり質問することで矛盾点を潰したり、業者の対応を確認しておいたりすると、ある程度の信頼を寄せて工事を依頼することができます。
4-4. 住宅ローンに解体費用を組み込む方法
住宅ローンに解体費用を組み込むことも、ひとつの選択肢です。一度に大きな金額を支払う負担を軽減できるため、金銭的・心理的に負担も少なくなります。
①金融機関に相談する
解体費用を住宅ローンに組み込む場合、まずは金融機関に相談して、どのような条件で融資が受けられるか確認することが必要です。解体工事では、解体ローンや住宅ローン、プロパーローンなどを利用することができます。また金融機関によっては、解体費用を含むリフォームローンや建替ローンを提供しているところもあります。
②ローンの返済計画を立てる
言うまでもありませんがローンを組む際には、返済計画をしっかり立てることが大切。無理のない返済スケジュールを計画し、将来的な負担を軽減することを目指しましょう。
5. まとめ
解体工事のイメージはつきましたか?
「家を取り壊す」作業なだけに、それにかかる人員も金額も大掛かりですが、ひとつひとつ取り組んでいけば難しいことではありません。まずは上記でご紹介した手順で、解体工事の見積もりから初めてみてくださいね。
もしお困りのことなどがあれば、【おうちのアラート】までご相談ください。