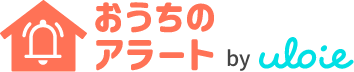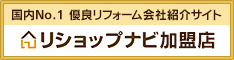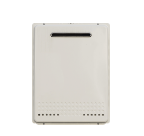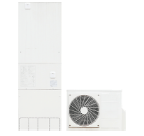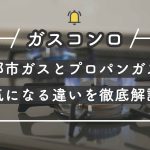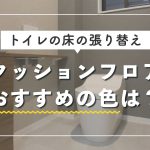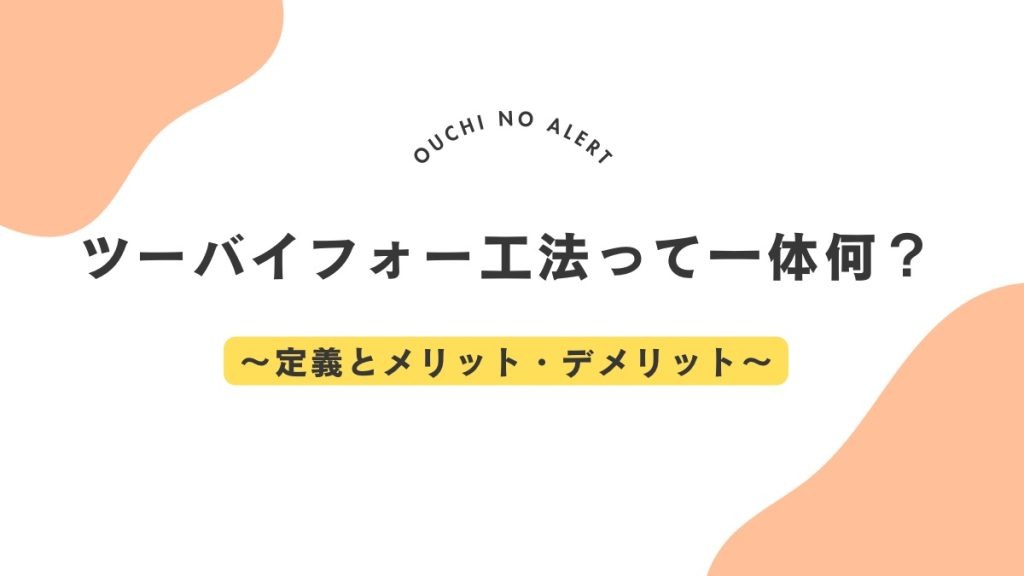
「ツーバイフォー」というこの言葉、DIYや建築に興味のある方は一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか?この工法は、強度や耐震性、耐火性に優れ、施工期間が短いことで知られています。
そこで本記事では、ツーバイフォーの定義やそのメリット・デメリットについて詳しくご紹介します。マイホームを建てる予定のある人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
1. ツーバイフォーとは一体何か

ツーバイフォー工法の大きな特徴は、床や壁などの「面」で建物を支える「面構造」であること。
建築基準法上では「枠組壁工法」と呼ばれ、約2インチ×約4インチの木材を組み合わせ、構造用面材と呼ばれる板を専用の金具で一体化させます。これにより、頑丈な六面体構造が形成され、地震や台風などの負荷を分散して建物の変形や崩壊を防ぎます。さらに、気密性や耐火性、省エネルギー性、遮音性にも優れています。
「ツーバイフォー」の名前の由来は、使用する木材の規格が約2インチ×約4インチであることから。部位によっては、2×6材、2×8材、2×10材、2×12材なども使用されます。
2. ツーバイフォーの木材サイズ

ツーバイフォー工法の名称は、主に2×4材を使うことから来ていますが、用途に応じて2×6材、2×8材、2×10材、2×12材なども使用します。
例えば、2階以上の床には強度を持たせるために2×10材を、外壁には断熱性を高めるために2×6材を使用します。
| 名称 | サイズ |
|---|---|
| 2×4材 | 38mm×89mm |
| 2×6材 | 38mm×144mm |
| 2×8材 | 38mm×184mm |
| 2×10材 | 38mm×235mm |
| 2×12材 | 38mm×286mm |
| 4×4材 | 89mm×89mm |
3. ツーバイフォーのメリット

ツーバイフォーは1974年に日本で認可されて以来人気の工法ですが、一体どのようなメリットがあるのでしょうか?以下でチェックしていきましょう。
3-1. 強固で耐震性が高い
ツーバイフォーは、部屋ごとに6面で支える構造のため非常に頑丈です。建物の重さや地震、台風などで発生する縦方向と横方向の力を建物全体で受け止めて分散し、変形や崩壊を防ぎます。
3-2. 耐火性が高い
ツーバイフォーは火災に強いのも大きなメリットと言えるでしょう。床や壁の内側に使われる枠組材がファイヤーストップ材となり、火の流れを遮断します。
また、全ての天井や壁の内側に厚さ12.5mm以上の石こうボードが貼られており、炎が当たると熱分解を起こして水蒸気を放出するため、火災が発生しても温度上昇を抑えます。これにより、構造材が発火点に達するまでの時間を遅らせることができます。
3-3. 施工期間が短い
ツーバイフォー工法は、壁パネルや床パネル・屋根材を工場で生産し、現場で組み立てる建築方法です。現場での複雑な手順が発生しないため、作業スピードが速く、結果として在来工法よりも工期が短くなります。
4. ツーバイフォーのデメリット
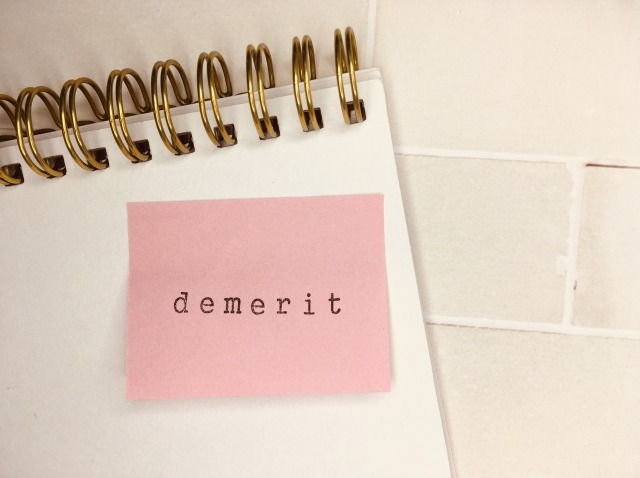
メリットの多いツーバイフォーですが、もちろんデメリットも。
ツーバイフォー工法は、パーツの規格が決まっていることから、在来工法に比べて間取りの自由度が高くありません。変形の部屋や大きな開口部、壁のないワンフロアなどは難しく、リノベーション時にも制約が生じます。
例えば、部屋数を減らし広い間取りにしたい場合や壁を移動させて廊下を広くしたい場合などにも、構造壁を使用している場合には対応が難しいことがあります。これらのデメリットを踏まえたうえで、使用の可否を検討してみてください。
5. まとめ
ツーバイフォー工法は、頑丈さや高い耐震性、耐火性に優れ、施工期間も短めという優れもの。しかし一方で、間取りの自由度が低いというデメリットもあり、建築の際には総合的に判断しなければいけません。
建築を考える際には、ツーバイフォーの特性を理解し、上手に活用していきましょう。